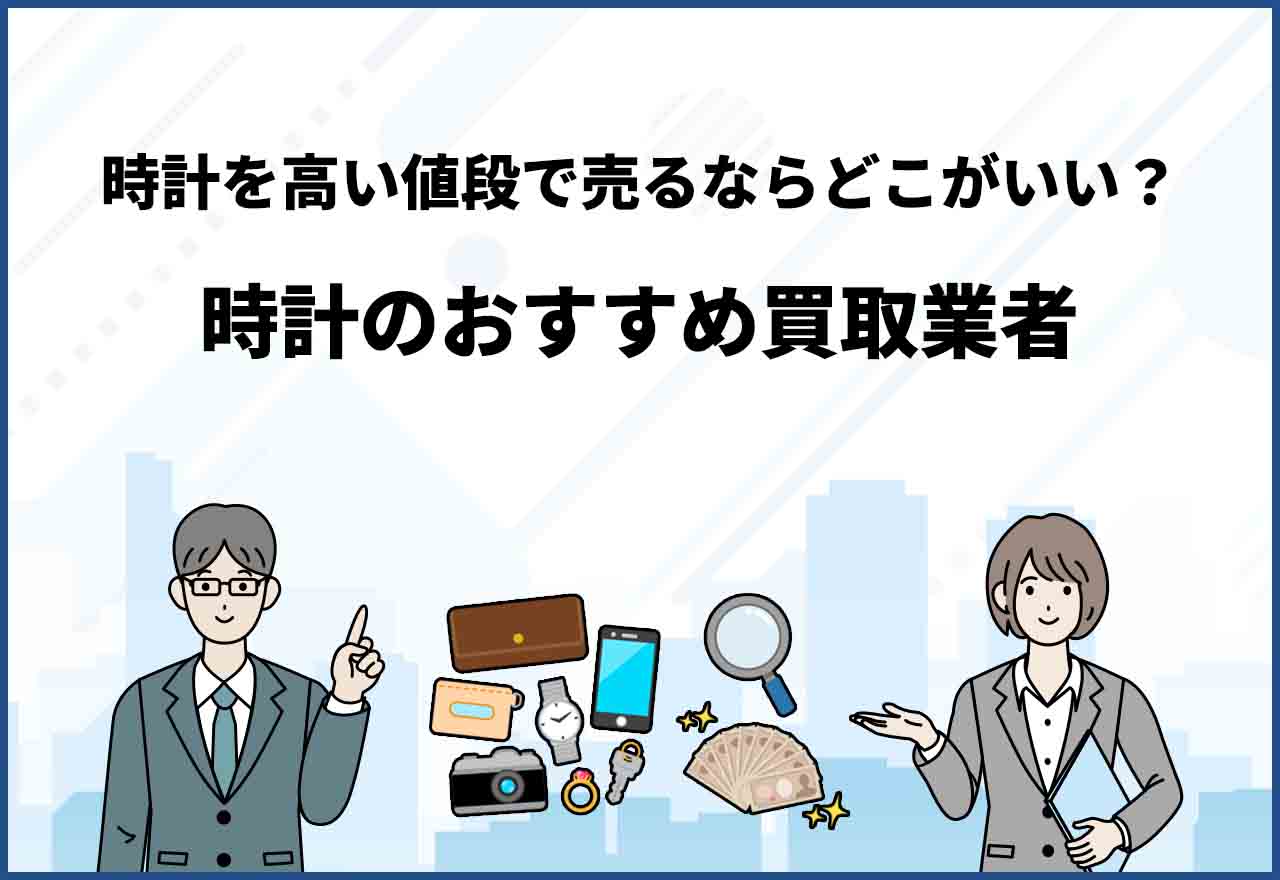◆最適な着用時期 10月~翌年5月の袷頃
◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません
◆着用シーン 結婚式、式典、パーティー、お付き添い、音楽鑑賞、観劇、お食事会など |
【着物】
絹100%
たち切り身丈182cm 内巾36.5cm (最長裄丈約69cmまで 最長袖巾肩巾34.5cmまで)
白生地には丹後ちりめん地が使用されております。
【帯】
絹100%(金属糸風繊維除く)
長さ約4.35m(お仕立て上がり時)
西陣織工業組合証紙No442 梅垣織物謹製
おすすめの帯芯:綿芯「松」
耳の縫製:袋縫い
六通柄 |
|
|
【 バイヤー&パーソナルカラー診断士 更屋より 】
――日頃より京都きもの市場をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
日々の感謝を込めまして、バイヤー&パーソナルカラー診断士の更屋がお得な秋の着物・帯のセットをご用意いたしました!
皆様にキンモクセイの香りに四季の移ろいを感じていただきたく、こだわりの良きものをコーディネートいたしました。
どうぞ、ごゆっくりとご覧くださいませ。――
フォーマルの装いに確かな品格と上質を…
手描京友禅染匠『岡山工芸』より
正統派古典柄の特選訪問着と西陣の名門『梅垣織物』より
特選袋帯を合わせてご紹介いたします。
秋風に揺られる金色の欅…
黄落すると黄色の絨毯となる情景をイメージして
コーディネートいたしました。
上品な彩りで古典の意匠をのセットは
式典へのご参列や入卒式などのお子様行事のお付き添いなど…
様々な社交シーンで重宝していただけることでしょう。
お目に留まりましたらどうぞご検討くださいませ。
【 お色柄 】
≪着物≫
さらりとしなやかな手触りの絹地。
地色はふうわりと淡い薄卵色に染めて、上品な印象に。
意匠には古典の冊子文様が草花とともに丁寧に描かれました。
挿し色は上品に映え、金彩のあしらいがそっと華やかさを加えて。
全体にすっきりとした印象を与える構図の美しさ、丁寧な加工、
どれをとっても本当に素晴らしく、確かな匠の風格が存分に満ち溢れております。
≪帯≫
ややハリのある、しなやかな地風のライトベージュ地に、
経糸に金糸をふんだんに織り込み、金糸の濃淡に落ち着いた
彩りの絵緯糸使いで、露芝や麻の葉、松皮菱、青海波などの
割付紋様を込めた変わり市松が織りだされております。
お締め頂きました際の帯姿としても格調高く、
華のある装いとこだわりの風合いを
ご堪能いただけることでしょう。
【 岡山工芸について 】
日本で初めての手描友禅・女性伝統工芸士・岡山武子氏(平成18年には史上初女性の友禅師「京都府伝統産業優秀技術賞・京の名工」として授章)をはじめ、
手描友禅のスペシャリストである伝統工芸士が3名、
職人約20名ほどが集う、まさに、手描き友禅の職人集団でございます。
その実績は、呉服の世界や日本に留まらず、海外においても広く認められております。
京都きものコレクションやファッションカンタータfrom Kyoto 、
パリ・コレクション等ファッションショーや雑誌、テレビ等メディアなどでご存知の方も多いかと存じます。
【 西陣織について 】
経済産業大臣指定伝統的工芸品(1976年2月26日指定)
多品種少量生産が特徴の京都(西陣)で
生産される先染の紋織物の総称。
起源は5?6世紀にかけて豪族の秦氏が
行っていた養蚕と織物とされ、応仁の乱を期に
大きく発展した。
18世紀初頭の元禄~享保年間に
最盛期を迎えたが、享保15年(1730年)の
大火により職人が離散し大きく衰退。
明治期になりフランスのリヨンよりジャカード織機を
導入した事でこれまで使用されてきた空引機
(高機)では出来なかった幾多の織物が
産み出され量産が可能となった。
織機はおもに綴機、手機、力織機の3種類で
企画・図案から意匠紋紙、糸染、整経、綜絖、
金銀糸、絣加工等多くの工程があり、これらの
一つひとつの工程で熟練した技術者が丹念に
作業を行っている。
西陣織には手の爪をノコギリの歯のように
ギザギザに削って図柄を見ながら織り上げる
「爪掻本綴織」、「経錦(たてにしき)」、
「緯錦(ぬきにしき)」、「緞子(どんす)」、
「朱珍(しゅちん)」、「紹巴(しょうは)」
「風通(ふうつう)」、「綟り織(もじりおり)」、
「本しぼ織」、「ビロード」、「絣織」、「紬」など、
国に指定されているだけでも12種類の品種がある。
「西陣」および「西陣織」は西陣織工業組合の
登録商標である。
【 京友禅について 】
経済産業大臣指定伝統的工芸品(1976年6月2日指定)
京都府知事指定伝統工芸品
京都の伝統工芸品の1つで古来の染色技法を
扇絵師の宮崎友禅斎が大成したもの。
元禄時代に京都で生み出された友禅技法で
日本三大友禅(京友禅、加賀友禅、
江戸(東京)友禅)の1つ。
「糸目糊」という糊を用い、筆で色付けする際に
滲んで色移りすることを防ぐ防染技術が用いられており、
基調の色が決まっておらず、当時の公家や大名好みの
デザインに多彩かつ鮮やかな色合いや金銀箔、刺繍などが
用いられた絢爛豪華、かつひときわ華やかな印象のものが多い。
明治時代には化学染料と糊で色糊を作り
型紙によって友禅模様を写し染める「写し友禅染め」が
友禅染めの中興の祖と称えられる廣瀬治助によって
発明され、「型友禅」として大量生産が可能となった。
量産できるようになった友禅染めは一気に普及し
飛躍的な発展を遂げ、昭和51年6月(1976年)には、
経済産業省指定伝統的工芸品として指定を受け、
現在も世界中から高い評価を得ている。
|
|
お仕立て料金
解湯のし4,180円+※胴裏8,250円~+海外手縫い仕立て35,200円(全て税込)
※国内手縫い仕立て+17,600円(税込)
※堅牢染め・本加賀など、染めのしっかりした御着物への抜き紋入れには、
堅牢抜き代4,400円(税込)が必要となります。
加工(湯のし、地入れ、紋地入れ)
(解湯のし)
撥水加工をご要望の場合
(ガード加工 帯)(パールトーン加工 袋帯)
|
※着姿の画像はイメージ写真です。柄の出方が少々異なる場合がございます。 |
|
|
| [文責:更屋 景子] |